
|
5 炭焼き体験[文化祭企画]
地球環境問題については、地球の温暖化、酸性雨、熱帯林の破壊、砂漠化、オゾン層の破壊など教科を越えて理解しています。しかし、身近な問題としての認識はあまりないようです。それは毎日出るゴミの山(ジュース缶・パンの袋)で教室は汚れているからです。知識としていろいろなことを知っていても、実際にその知識をもとに行動ができなければ、「真の知識」とはいえないと思います。
アウトドアーブームによって炭が見直されてきています。炭焼きが各地の山間地で行なわれるようになれば林業が復活し、日本の山がよみがえることになります。日本の国土面積の67%が森林で覆われています。しかし、外国の安い木材が輸入され、国産材は売れなくなり日本の山は荒れていることも事実です。東南アジアで伐採された熱帯林の行き着く先は日本であることは誰でも知っています。
炭を焼くことで日本の文化に触れ、木に関心を持ち、森林の役割とは何かを考えながら炭焼きに挑戦することにしました。
日時:1泊2日10時開始〜12時終了
場所:学校内の空き地
主催:地理同好会
参加1顧問・同好会員・有志
(1)伏せ焼き法の特徴
炭窯を築かないで炭焼きが出来る、最も簡単な方法
(2)準備
器材・資材
スコップ・なた・つるはし・メジャー
のこぎり(4個)・軽量ブロック4個
煙突(径10?pL=100?p)1本
トタン(60c皿×210?p)2枚・ポール
林地残材(林地に放置されている間伐材、伐竹材など)
工場廃材(背板・鋸屑)、勇定枝・スギの枝葉・ワラ・刈り草・もみがらなど・炭材の長さ60cmに切る。
(マテバシイ・サクラなど)
・径10cm以上の炭材は割ること。
伏せ焼きの炭材は、よく乾燥しているのがよい。
(3)装置の作り方および炭の焼き方
?@製炭の場所
乾燥した平坦な場所で、周囲が空き地になっている場所選ぶ。
ばい煙が周囲の住民に迷惑をかけない所で、水の便利なところを選ぶ
?A床堀
風の吹込む方向に穴をほる。
奥行:180?p・幅:100cm・深さ:30cm
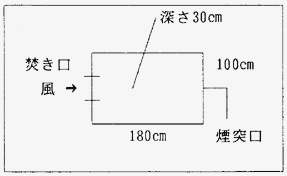
製炭場所の設定
窯底は平坦に仕上、よく踏み固める
穴の中で焚火をして、窯底を乾燥させる
?B焚き口
焚き口になるところは、太い丸太(径12cmL=30cm)を2本置く。間隔は、
27?pとする。この上に、太い丸太を3〜4本積み上げて作る。
?C排煙口
排煙口についても、焚き口と同じように作り、煙突を取り付ける。
煙突がずれないように取り付ける。
?D点火室
?Bの焚き口の前に、軽量フロックを2本置く。間隔は、27cmとする。その上に、
前ページ 目次へ 次ページ
|

|